壺と甕 | それぞれの用途と特徴
壺と甕について
壺(つぼ)と甕(かめ)はそれぞれ古くからある器形として馴染みのあるものです。古くは飲食物の貯蔵容器や煮炊き用の調理具のほか、火葬した遺骨を納めるものとして使われました。現代では多種多様な容器として、もしくは草花を活ける花器、飾って楽しむ調度品として広く用いられています。
大型のものは美術館やインテリアショップ、または飲食店などでも大壺や大甕が飾られているのを目にすることもあります。屋内に鎮座する大壺に花が活けてある場合もあれば、大甕に水を張って金魚やメダカを泳がせている光景にも出会います。
一方、小型のものであれば一般家庭でも実用の器として使われています。たとえば床の間や窓際に小壺を置いて花を挿すこともあれば、焼酎や日本酒を注いで酒器として用いる場合もあります。
小型の甕は一般的ではありませんが、我が家では備前の小甕にカレーなど調理で使うローリエ(月桂樹の葉)を入れています。甕は壺よりも口縁が広いため中身が取り出しやすく、乾燥にも適しているうえローリエの香りも楽しめます。もちろん花器や酒器としても使えますね。
さて、このように壺と甕は割と身近にあるうつわといえます。両者の違いは曖昧になっていることもありますが、厳密にいえば区別される特徴がそれぞれあります。
壺の形と用途について
壺は口がすぼまっていて胴が膨らんだ形状が特徴です。胴が広いので背が低いものでも、入れ物としての容量があります。さらに口が狭いおかげで外気に触れる面が少なく中身を長期保存できます。
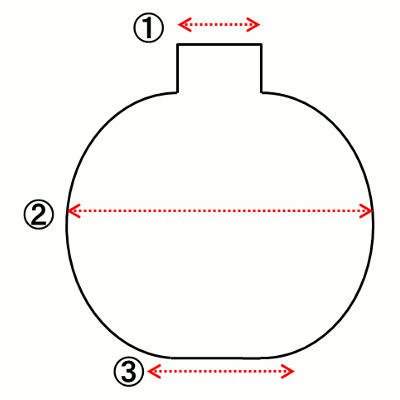
簡略化した図で恐縮ですが、1の箇所を「口」、2は「胴」、3を「底」として比較してみます。口の部分はすぼまった形で、胴が膨らんでいますね。そして底は口よりも幅が広い形状が特徴です。
このことから、壺の形状で食べ物や飲料を入れる場合は少量の出し入れに適していることが分かります。口が狭いので外気に触れにくい利点を持つ一方、出し入れをする際は少しずつしかできないという事が分かります。
たとえば酒であれば空気に触れることで、アルコールと香りが飛んで劣化が進みますが、壺のように外気に触れにくい形であれば長期保存にも適しています。そして小分けに徳利に注ぐ場合でも少量ずつであれば十分に事足ります。
ちなみに一升瓶は縦長で壺と形こそ異なりますが、口は狭く底は安定性を高めるため口より広い形状ですね。栓は小さなもので済みますし、仮に栓を開けた状態でも中身が劣化しにくいわけです。壺の長所(=口が狭く底が広い)を取り入れ、細長いことで収納にも優れた一例です。
また、壺を花器で使う場合は口がすぼまっているためたくさんの花を挿すことはできません。ですが挿し口がキリッと締まっていることで、一輪挿しのようなシンプルなものでも全体的にバランスが取れます。
以上のことから、壺の形は「口が狭く胴が膨らみ、底は口よりも広い。すなわち内容物が外気に触れにくい形」。用途としては「少量の出し入れに適している」とまとめられます。
偏壷
甕の形と用途について
甕とは口が広く胴の2/3以上のものを指します。そして胴から底に向かってすぼんだ形がその特徴です。
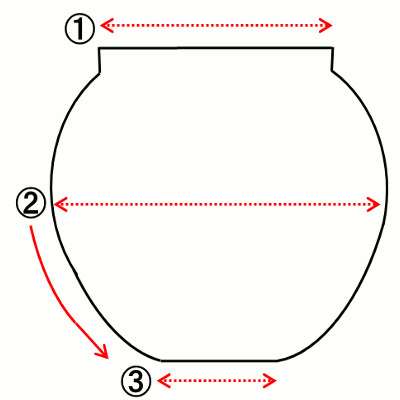
1「口」、2「胴」、3「底」として比較すると、口と胴の幅がほとんど同じくらいであることが分かります。そして胴から底に向かってすぼんでいくため、底の幅は口・胴より狭くなっています。
甕の大きな特徴は口の広さにあります。したがって食物や飲料を入れる場合は大量の出し入れに適しているといえます。
フタをしなければ外気に触れやすいため、内容物によっては長期保存に適さないこともあります。しかし短期的に大量の出し入れをする場合、甕の大きな口は使い勝手のよい形をしています。
以前ある飲食店で壺と甕を使い分けている光景を目にしました。まず壺には泡盛(あわもり:琉球諸島産の蒸留酒)が貯蔵されていて小さな木栓がしてありました。聞けば陶器に入れておくことでアルコールの角が取れて飲みやすくなるとか。
普段は木栓をすることで蒸発を防ぎ、使った分は壺に注ぎ足して貯蔵しているのです。注文すると壺からガラスの徳利に注いで出してくれました。
そして甕の方には焼き物で使うタレが入っていました。焼き鳥を注文すると口の広い甕に串を浸してサッと引き出して炭火で焼いてくれます。
どちらも液体(酒とタレ)の貯蔵容器として使われていたわけですが、少量ずつ小出しにするための「壺」、一度にたくさんの串を出し入れするための「甕」。それぞれの用途がはっきりと分かりました。入れ物が逆では当然使い勝手が悪いでしょうね。
甕の特徴を一言でいえば「口が広い(具体的には胴の2/3以上の幅)」とまとめられます。用途としては「大量の出し入れに適している」といえます。
煮炊き用の甕について
前述のとおり甕は口が広く、胴から底に向かってすぼんだ形と述べました。その中でも極端に底が狭いものがあります。作るさいには口縁部から紐状の粘土を積み上げ、逆さまの状態で焼いたのでしょう。
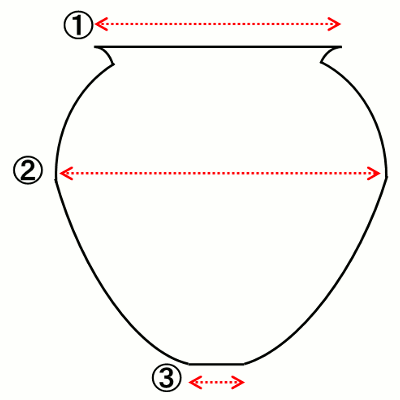
こうした形の甕は、古くは縄文時代後期~弥生時代に作られていました。図を見るととても不安定な印象を受けますが、実際は地中に埋めて使われたといわれています。
当時は必ずしも平らな調理場があったとは限りませんね。そこで底を埋められる形にして地面でがっちり固定したわけです。
胴から下の方は地中にあって、横幅の広い胴のあたりを直火で加熱したと考えられています。というのも、出土品の胴まわりに火が当たった煤(すす)が付いたままのものがあるからです。こうした甕型の土器で縄文後期~弥生時代の人々は煮炊きをしたのでしょう。
また、口縁はより広くなるように外側に向かって反り返っています。こうすることで食物の出し入れが容易になります。壺と甕に見られるその形状は実用のうつわとして先史時代に産声を上げ、現代でもその形を目にすることができます。
