陶磁器ができるまで 工程と用語
一般的な工程は素地をよく揉んでから成形、素焼き、施釉、本焼きの順で行われます。時系列でそれぞれ説明させていただきます。
荒練りと菊練り
成形前に素地を揉む工程です。荒練りの目的は粘土全体の水分量と硬さを均一にすることです。
粘土全体の水分量が均一にならないと、形を作るさいに障害となります。たとえば土の一部が柔らかいのに対し、別の部分が硬くヒビ割れなどが起きてうまく成型できなくなります。
特にロクロで水曳きするさいに、水分量がバラバラだときれいに挽けません。水分の乏しいところが硬い塊になり、周りの柔らかい部分がちぎれたりします。こうした事態を防ぐためにも荒練は必須の作業です。
次の菊練りは粘土中の空気を抜くために行います。揉んだあとが菊みたいな模様になるため「菊練り」と呼ばれます。
粘土の中に空気が残っていると、乾燥時には分からなくても素焼きしたさいに破損の一因になります。これはイメージ図ですので、実際の私は粉々になった残骸をため息まじりにただ眺めていました(笑)
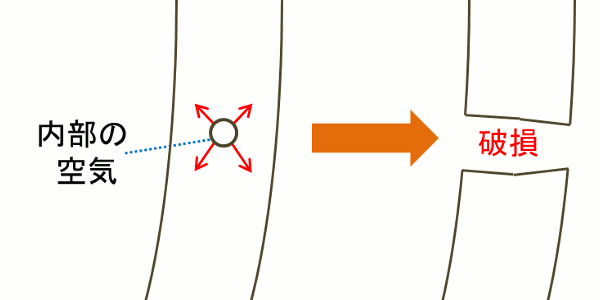
焼成は高温でおこなうため、たとえ小さな空気だとしても膨張しようとします。そして内部に空洞があれば貯まった水分も乾燥しずらくなります。その結果、内部の閉じ込められた空気(および水蒸気)が作品を圧迫して内部から割れてしまうんですね。
また粘土の中の空気が、何かの拍子に抜けることもあります。特に高台や底の内部に空気が閉じ込められていた場合です。乾燥させると、空気が抜けた部分が歪んだり傾いてしまうこともあります。
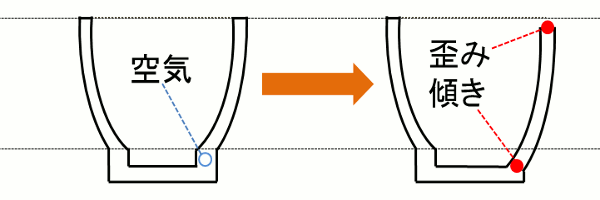
このように粘土内部の空気は、閉じ込められても抜けたとしても問題になります。これを防ぐため水分量を均一にして空気を抜くという、荒練りと菊練りは大切な作業です。
さらに荒練りと菊練りを丁寧に行うことで、上記のようなトラブルを低減させるだけではなく、素地の粘りが増すため形を作りやすくなります。
現在ではこの作業を機械で行うこともできます。土練機(どれんき)と呼ばれる機械で、水分量を均一にして空気を抜いた状態にしてくれます。
粘土を機械に放り込んで待つだけなので作業も楽になります。棒状に押し出された粘土は成型しやすい状態に調整されます。その利便性から土練機は大量の粘土を扱う現場に普及しています。
はじめて見たときは感動しましたが、機械で簡単にできてしまうと味気ない気もしますね。土練りははじめはとても大変ですが、土の感触がじかに分かるので未体験の方にお勧めです。
成形
主にロクロと手びねりで成形します。ロクロは手動・電動ともに均衡のとれた成形と量産に適しています。手動の物では手ロクロ、蹴(け)ロクロがあります。
ロクロは多くの製作現場で使われています。この画像は蹴ロクロを使っている様子です。基本的に手で成型し、牛ベラで形を微調整しています。
いっぽう、手びねりとはロクロを使わず手作りで成形することです。大物作りや量産には向きませんがロクロと違った成形ができます。全て自分の手で形を作っていきます。
こうした手作業で有名なのは樂茶碗が挙げられます。樂では「手づくね」といいますが、作者の手なりがそのまま出ますので個性的な作品ができあがります。
次にヘラで粘土を削っていきます。削りの意図は余分な土をそぎ落として形を整えることです。
極端に厚い部分があれば削って均等な厚さにしていきます。削り作業で手に持ったさいの重さをほどよく調節し、凹凸がなくなって手取りがよくなります。
また、粘土が厚い部分にはどうしても水分量が多くなります。水分量が多いと乾燥させたときの収縮が大きくなったり、焼成時に水分が残っていると破損(水蒸気爆発)が起こるなど…なにかと問題になります。
たとえば湯飲みを作るとしましょう。全体を指で触って分厚い箇所があれば土をそぎ落とします。口をつける口縁部の厚さを自分好みに調整します。
私であればやや厚めで丸みを帯びた口縁がいいですね。この場合は丸みを持たせたいので、ロクロを回しながらなめし革で口縁を丸くします。
そして腰まわり(半分から下の部分)を引き締めたいとすれば削って微調整します。また、高台まわりに土が多いと重心が底に集中します。下部が重いと湯飲みを傾けて飲むときに具合がよくありません。そこで余分な土を削り落として重さも加減します。
こうした削りが済んだらしっかり乾燥させます。乾燥が不十分だと内部に水分が残ってしまいますね。その結果、焼成中に高温の水蒸気により破損するおそれがあります。
まとめますと、全体の形を作ってからヘラ削りとなめし革で微調整する。そして十分に乾燥させるという工程です。
素焼き
600℃~800℃程度で仮焼きする工程です。素地が割れないよう徐々に温度を上げていき、まず表面の不純物を焼き尽くします。
素焼きの大きな目的は釉薬を吸収する下地を作ることです。
釉薬(ゆうやく)とは陶磁器の表面を覆うガラス質のことです。釉薬は本焼きをすることでガラス化しますが、ここでは簡単に「灰を水に溶いたもの」と考えてください。
素焼き前の粘土は釉薬を吸収しづらい状態のままです。この画像は素焼き前の乾燥した粘土の表面です。
乾燥した状態で黒っぽい有機物などが見て取れますね。これを素焼きすると有機物が焼きつくされます。そして細かい穴が作品全体にできて釉薬を吸収しやすくなります。
こちらが素焼きした粘土の表面です。有機物が焼けて表面が多孔質になって立体感が出てきています。
素焼きの身近な例として「植木鉢」が分かりやすいです。素焼きされた植木鉢は表面がザラザラしていますよね。土を入れて水をあげても、植木鉢が余分な水分を速やかに吸収し、表面の細かい穴のおかげで吸収した水分が蒸発しやすい構造になっています。
これをただの粘土で行ったらどうなるでしょうか?表面に小さな穴が乏しく水分をなかなか吸収してくれません。そして水を吸うと柔らかくなって崩れてしまいます。
つまり、植木鉢のように素焼きをすることで「水(陶芸の場合は釉薬)を吸収しやすくなる」。「水分を吸収しても崩れなくなる」とまとめられます。
あとは素焼きによって作品自体の強度が増します。たとえば半乾きの粘土を触ると簡単に跡がつきますが、素焼きした粘土は軽くぶつけたくらいでは何ともないくらい硬く焼き締まります。これも植木鉢を連想すれば分かりやすいでしょう。
素焼きをしたら釉薬をかける作業にすすみます。
施釉
釉薬をかけることを施釉(せゆう)するといいます。釉薬はたくさんの種類がありますが、ここでは「灰と水」と簡単に考えてください。
これはバケツに入った灰釉をかき混ぜている画像です。灰に水を加えてよく混ぜることで釉成分が均一化します。そして素焼きした素地に水ごと吸収されます。
釉薬を十分にかき混ぜたら、素焼きした作品に施釉します。素焼きされた素地は釉薬を吸収しやすい状態になっています。
施釉方法は何通りかあります。一般的な方法を挙げるとすれば、まず釉薬に作品をそのまま浸す「ズブ掛け」「浸し掛け」。そして筆や刷毛などで釉薬を塗る「筆塗り」「刷毛塗り」が挙げられます。
ズブ掛けは作品全体に均一に施釉することができます。施釉しない部分(たとえば碗の高台など)を指でつまみ、作品を釉薬に数秒ほど浸します。そして引き上げたら水気を切って施釉完了です。
ズブ掛けの利点は短時間で全体に施釉できる点と、すっぽり浸すことで釉薬の塗り忘れがない点といえます。
なお作品のサイズによってズブ掛けができない場合もあります。たとえば釉薬の容器より大きな皿や壺などです。この場合は大皿を回しながら柄杓で釉薬をたらしながら施釉する「流し掛け」。もしくは霧吹きで壺全体に施釉する「吹き掛け」などが有効です。
さて、筆塗りの場合は細かい施釉ができます。たとえば釉薬を薄くしたい箇所は薄めに塗り、厚く施釉したい部分は何度も重ね塗りができます。作品全体の釉の厚みや表情を調整する場合に適しています。
こうした方法で釉薬をかけるのが施釉の工程です。施釉後は本焼成にむけて十分に乾燥させます。
本焼成
1,000℃~1,300℃で本焼きをする工程です。高温によって素地はより焼き締まり、熔けた釉薬はガラス質になって表面を覆います。
作品を焼くための窯は「薪窯」「灯油窯」「ガス窯」「電気窯」に大別されます。現代では排煙や燃料の問題によって、薪窯は減少傾向にあります。
その一方で、電力を使って熱線で焼く電気窯が普及してきました。設置スペースと音の問題がクリアできる環境ではガス・灯油窯も活躍しています。
電気窯やガス窯は、薪窯とくらべて昇温も容易という利点があります。ただし温度管理が楽になった一方で、薪窯特有の自然な焼き味は失われつつあると思います。
焼成温度は素地の種類・収縮率・釉薬・焼成方法により変わります。おおむね陶器の焼成温度を1,100℃前後とした場合、磁器は+100℃~200℃位が目安となるでしょう。
焼成には大きく分けて二つの状態があります。1つは窯の中の酸素が十分な状態で焼く「酸化焼成」。もう1つは酸素が乏しい状態で焼き上げる「還元焼成」。
酸化・還元の状態によって釉薬は多様な発色をします。たとえば透明に焼きあがる灰釉に微量な鉄分を含んでいたとします。
これを酸化焔で焼くと黄色をおびた釉色になるのに対し、還元焔の場合では青味を帯びた釉色になります。青磁などは後者の還元焼成で得られる色彩です。
こうした窯の中の状態を「雰囲気」と呼ぶことがよくあります。
たとえば「薪窯で序盤10時間ほどは還元雰囲気で焼成し、あとの14時間は酸化雰囲気で後半の数時間は練らす」という表現があったとしましょう。
これを翻訳すれば「はじめは燃料をたくさん入れて10時間ほど酸素が乏しい状態で焼く。後半は薪が尽きそうなタイミングで燃料を足し、酸素が十分な状態で14時間焼く。そして終盤は数時間一定の温度を保つ」という意味です。
ちなみに「練らす」とは「その状態(温度)を保つ」ということです。「ねらし焚き」とか単に「ねらし」といいますが、要は一定の温度をキープしてじわじわと釉薬を熔かす仕上げ段階と考えてください。
また焼成温度や焼成雰囲気に加え、大切なのは焼成「時間」です。素地を焼き締め釉薬を熔かすには温度だけでは足りないのです。徐々に昇温しながら1,200℃の高温になったとしても、釉薬は一瞬で熔けるわけではないからです。
たとえば1,200℃で10時間かけてやっと釉薬が熔けたとします。このケースであれば1,200℃という「温度」に加え、10時間という「焼成時間」が必要ということになります。
この場合、仮に温度が1,100℃であっても15時間焼成したら釉薬が熔ける可能性も十分あります。このような温度と時間の関係が重要となります。
本焼成後、十分に窯の温度が下がってから作品を取り出して作業完了です。ちなみに高温の状態でわざと取り出す「引き出し黒」もありますね。
窯から出した作品に対し、出荷前の検品を行います。歪みや割れ・カケはないか、釉はしっかり熔けているか。薪窯焼成であれば灰をかぶっている作品は水とブラシで灰を落とします。
そして口をつける口縁部や、接地部である高台にバリ(出っ張りや突起)があればヤスリで丁寧に磨きます。茶碗や酒器など液体を注ぐ作品であれば水漏れの有無も確かめます。こうした工程を経た作品が私たちのもとにやって来ます。
このページでは陶芸作品ができるまでの概要を述べました。たとえば施釉前に絵付けをする「下絵」や、本焼成後に絵付けをする「上絵(うわえ)」、各種装飾技法については省かせていただきました。
各技法の詳細については、当サイトの「陶芸技法」の目次をご参照ください。
